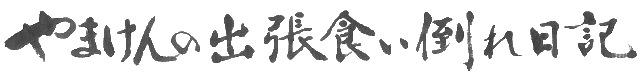
ご覧の通り、フグ刺し用の皿か!という大皿に盛り込まれた土佐ジローの肉。これを炭火で焼いていただきます。
ちなみに正肉部分は一羽分で、肝類一式が4羽分だそうだ。なみに食べ迎え撃つメンツは4名、正肉の量はこれで十分という感じだ。
やっぱりね、結論から言っちゃうと、鶏の肉は可能な限り色んな部位を食べるのが楽しい。ついつい家庭ではモモ肉だけとか胸肉だけとかになりがちだけれども、こうしてみるだけでも、肉の線維感も色もテクスチャもすべて違う。ということは、味わいも変わるのだからね。
さて、焼くと言っても、よくある、肉だけ出しておいて、客に任せるようなことはしません。
「土佐ジローはね、焼き方を一歩間違えると美味しくないけん、一通りは僕らが必ず焼かせてもらいます。焼き加減で味が変わるんでね!」と、小松精一さんの登場である。
まずはモモ肉から。皮面を炭火にあてて焼き始め。もう30年以上も、自分が育てた土佐ジローを焼いている人だ。どの部位をどのように火入れすれば良いのか、この人以上にわかっている人もいないだろう。
焼き鳥という料理ジャンルは日本で独自の発展を続けているが、話しをきいてみると、きちんとした焼き手であれば一人一人がそれぞれの理論を持っていて、微妙に違えども、結果的に食べてみると「美味しい!」となることが多い。
精一さんの焼き方は、いっけん無造作にみえるだろうが、火の熾り方を観て、肉にあたる熱気を積算し、わりとめまぐるしく返していく焼き方だ。大阪の「やまがた屋」のガタヤンの焼き方を観たことがあるが、彼も「割と僕はひんぱんに返すんだ」といっていた。それを思い出してしまった。
ちなみに炭も、地元である安芸市の備長炭を使っている。写真を観ればわかるとおり、かなり網面と近いところに炭が積まれている。これも試行錯誤の中でたどり着いた最適解だという。
みごとに焼き上がった土佐ジロー、皮付きのモモ肉。
焼き目はついていながら、こげ目はついていないということがわかるだろうか。そのこと自体、ひんぱんに返しつつやいたことを物語っている。
肉には振り塩をしてあるので、そのまま口へ入れる。熱い塊を噛みしめると、筋繊維の間に滞留していたであろう汁が、歯の圧力に耐えきれずジュバッと噴出する。その汁の香りが、また味わいも共に、強く清々しい! 彼らはうま味のみを追い求めた鶏肉ではなく、綺麗な味わいを追求しているのだと感じる。旨い!
続いて胸肉を皮目から並べつつ、白子を置いていく。
「白子はね、時間がかかるんで、いまから焼いていきます」という。ちなみに白子って、オスがもつ精巣だ。一羽にふたつ、着いています。
この胸肉がまた、とくだんに美味しかった!
夢中で食べてしまったので写真なし(笑) 美味しい地鶏肉は胸肉がひときわ美味しい。その真実はゆるがないね。モモ肉はよく動かすので、うま味は濃いけれども、筋繊維が複雑に発達しまくっているので、弾力が強くなりがちだ。それに対して胸肉は筋繊維が綺麗に揃い、その鶏の肉質を素直に受け取ることができる。土佐ジローの胸肉はとにかく美麗な食感にして、うま味が濃い。
網面では皮が焼かれている。
「僕はねえ、子供の頃には自分でいろんな野鳥をとって、さばいて、砂糖醤油に付け焼きにして食べてました。土佐ジローはね、他の鶏品種と違って、その時食べた鳥の味に近いと思うんです。いわゆるジビエに近い感じですね。」
と精一さん。なるほど、ブヨブヨしていないストイックな肉質はたしかにジビエのような精悍さを感じるところもある。ただ、味わいはとても洗練されていると思うけどね!
この皮の厚みを観れば、ジローの飼育期間がブロイラー(国産若鶏)の3倍に至ることがわかる。そして、皮なのに脂や水気がしみ出ていないのを観れば、引き締まった育ち方をしていることが、またわかるわけだ。
焼き上がった皮はグニュ感いっさいなく、シャキンと心地よくかみ切れてくれる。
ふたたびモモへ。
「こんどはゆず果汁をすこしかけて食べてみて下さい」
もちろん地元・安芸産のゆず果汁、ジローに合わないはずがない!
ちなみに振り塩してあるのも高知県産である。そもそも高知は「地塩」というべき、自前で製造している塩業者が多いのだ。
よーく育った土佐ジローの砂肝。
ジャキッと心地よい食感。これまた臭みまったくなく、生き生きとした味わいと香りがする。
「砂肝はねぇ、鶏にとって特別な器官だと思います。僕ら小さいときに、砂肝という臓器は、小石を食べて、穀物をこなすために石を土を食べると習いました。それは間違いではないと思うんだけど、それだけではないんじゃないか、と思うようになりました。鳥は飛ぶために骨を軽くしたり、臓器も小さく進化してきました。それなのに砂肝は、わりあい重いんですよ。ということは、たんに石をこなすための役割以上のものがあるんじゃないか。想像ですけど、土や石からミネラルを補給している役割があるんじゃないか。そうしたミネラル類の効果として、匂い、臭みを消すということがある。」
匂いを消す?
「はい、鶏は夜目が効きません。対して天敵は目もよかったろうし、鼻も人間の数百倍は利くハクビシンみたいなのが相手でしょう。そうした天敵に夜に襲われないためには、匂いを消す方向に動いたのではないか。その役割を担っていたのが砂肝なんじゃないかって思うです。」
ええっ そんなの初めてききましたよ!?
「じつは昨年の11月に、日本の獣医師学会でもお話しをさせてもらったんだけど、鶏が放し飼いで土を食べることのメリットとして、免疫緑や治癒力向上があるだろうなあと。というのも、友人がブロイラー品種を、通常よりずいぶん長い10ヶ月くらい飼いよったんですが、そうすると土や糞などで、足の爪の付け根辺りとか、すぐに化膿してかさぶたになってしまう。ところが土佐ジローは、土だけでなく小石まみれの環境なのに、足はツルンツルンで綺麗な状態で育ちます。この違いこそ、ジローに肉の臭みがないことと関係があると思うんです。」
と話しをききつつ、僕が大好きな血肝へ。
脂を含んでいるので、煙が盛大に立つ。とろんとした、鉄分とうま味の塊である。
そしてレバー。
レバーは、中が生のサッと焼きみたいな仕上がりではない。
ご覧の通り、火をキッチリ入れて、あいまいな部分はないのに、しっとりした状態にもっていく。健全に育った鶏のレバーの、臭みなく、ただひたすら濃密に溶けていく上質な油脂である。
おつぎは、はたやま夢楽ならではのたのしみ、トサカだ。
綺麗に下処理されたトサカは、つやっとした軟骨様の部位。そして、じつはヒアルロン酸の塊。
このようにきちんと全面に火を入れていく。
クリンクリンッとした食感、風味はそれほど強くなく、焼き入れることで臭みもない。
それと、これ、なんていう部位だったかなぁ、なかなか単体で食べることのない部位です。
ところで、一番最初に置いた白子がずーっとじんわり焼かれて、それをこうして冷ましているのに気づかれただろうか。
「お肉は熱々がいいんですけど、白子は焼いてからしっかり冷ますことで食感がわかり、また甘みや旨みがわかるようになるんです。食べてみて下さい。」
おお、昨日の白子よりも臭みがなくなって、ほんのりと甘みを感じる!そう、すこしだけ野性味というか匂いを感じたのだが、思い切って中心部まで熱を入れ、それをまた冷ますことで、味わいがわかりやすいようにする。日本酒の燗冷ましのような技術だ。これは美味しい!
「時間をかけてかけて焼いて、10分かけて冷まして。これが一番おいしい食べ方だと思うんです。もうちょっとレアでとか、もっと焼いてみようとか、自分がおいしく食べたくて工夫してきた結果、たどり着きました。どっかで課題みたいにやってたら続かなかったでしょうねえ。」
いやいや、脱帽だよ!
さて、これで一通りの焼きが終了。
「ぼく、もっとしゃべりたいんで妻に焼きを変わってもらいます根。お願いしてエエか? これね、焼き手が変わると味もちょっと変わるんです。」
ということで、圭子さんに交代!これがまた、ぜんぜん味わいが変わって面白い結果になるのだ!さらに続きます。