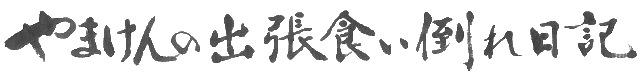

つい先日のことだ。土曜日だがどうしても仕事をしなければならず、午前中から日本橋の事務所にいた。11時過ぎにはなんとか終えたところで、凶悪に腹が減っていて、今日は自分へのごほうびにトンカツを食べようと決めた。
小舟町~人形町界隈ではいくつかのトンカツ専門店のチョイスがあるが、どこもとびきり、ということでもなく、でもトンカツに毎回とびきりを求めるわけでもないので、まあいいか、という選択をしてきた。ただしその時は、気分的にいつもと違う店にしようと思い、たわむれにGoogleマップでとんかつと検索してみたのだ。
そうしたら。いつも通勤で使っている地下鉄人形町駅からほど近いところに「あれっこんな店あったっけ?」という店名があった。その店名には、見覚えがあった。そこは居酒屋などが軒を連ねる路地裏で、決して目立つ場所ではない。まさか、その名が示す店だとしたら、そんな目立たぬ場所にあるはずがない。まあ、偶然そんな名前になったんだろうと思ったのだ。
でも一応はと思い直し、店名で検索をかけた。どうもおかしい、、、あの店っぽいのだ! なんと今年に入ってできたばかりだというが、まったく気づかなかった。
すこし興奮しながら電話をかけて、きょう営業しているか尋ねた。「11時半から2時までやっております」という。ちょっと緊張してしまい「あの、おたくはあの●●ですか?」と訊くことはできなかった。はやる気持ちを抑えて店に向かうが、無様なほどに足早になってしまっていた。
路地裏からその店の前に立つと、予感は確信にかわった。この裏路地にならぶ店とはまったく違う重厚でスタイリッシュな店作りのセンス。これは間違いない、あの店だ。
入店する。「いらっしゃいませ!」と迎えられたカウンター席。ああ、これだ。この雰囲気だ、、、
、、、
僕は大学院生のとき、静岡の製茶問屋さんのインターネット導入のお手伝いをしていたことがある。月に一度、泊まりがけで社員さんにネットのことを教えていた。そこの社長さんと専務さんに、一流の煎茶とはどんなものかを教えてもらい、煎れ方も伝授していただいた。そこの専務さんはかなりの美食家で、毎回のように「やまもとくん、旨いものを食べに行こう」と静岡のA級からB級まで、さまざまな名店に連れて行ってくれた。あの三次元トンカツの「蝶屋」も専務に連れて行っていただいたものだ。
ある日「やまもとくん、塩で食べるトンカツって、いままで味わったことある?」と訊く。もちろんない。その頃のぼくは、トンカツとはソースをおいしくいただくための媒体だと思っていたので、濃厚なトンカツソースをドボドボとかけて飯を何おかわりできるかということで店を評価していた(笑)
連れて行ってくれた店は、その店構えからしてふつうのトンカツ屋ではなく、料亭それも先鋭的にモダンな民芸調とでもいうべきかっこいい空間だった。
「特ロー(トクロー)2つ!」
と専務が頼むと、ほどなくして切られたトンカツがうやうやしく銅の網にのせられて出てきて、これまた初めてみる光景だったのでとにかくビックリした。その傍らには粘度の高いソースの入った小皿もあるが、その前にまず白の塩が入った小皿があった。
「塩をつけて食べてごらん」
といわれて口に運んだ一片がいまも忘れられない。上品な油の風味に、サクリと強めの立ったパン粉の衣、そして柔らかくシットリした肉質の肩ロースのうま味が、塩によって最大限に引き出されていた。あれほどソースをべたべたかけて食べるのがすきだった僕なのに、このトンカツは塩のほうがいい、と思ってしまったのだ。
「やまもとくんわかるかな?これ、市販の練り辛子じゃないし、マスタードでも無いんだよ」
と専務がゆびさしたのは、黄色い辛子が入った小皿だ。マイユのマスタードのように辛子の種の粒が混ざったそれは、実に高級感があった。なんと国産の辛子の種を買い求め、店で辛子を練っているという。マジか!?と思った。その辛子をつけると、とてつもなく風味がよく、辛さではなく爽快感を感じた。
社会人になって自分のお金で高級トンカツを食べられるようになると、恵比寿の百貨店の地下にできたその店の支店に食べに行くようになった。その後、その支店は名前と経営を変えて存続していたが、いつのまにか無くなってしまった。
あの店と同じ佇まいが、目の前に拡がっていた。
「あの、この店って、静岡の、、、」
と尋ねると、まだ若そうな店主さんが「はい、そうなんです。」と朗らかにおっしゃる。
「わたしがそこで修行をして、いま、静岡で、違う店名ではありますが、お店をやらせていただいてます。」
え、じゃあ、おやっさんはどうしているの?と思ったとき、二階からトントンと、一度みたら忘れられない濃い顔の親父さんが降りてきた。ああ、本当にあの店なのだ。
「じゃあ、『特ロー』で頼んでいいですか?」
「もちろんです。うちのトンカツはグラムをご指定いただきますが、250g以上ですと肩ロースを使います。それを特ローとしています」
店主は後ろの冷蔵庫からロース一本を取りだした。芯の比較的小さい、引き締まったロースだ。肩口部分を切り出して肉タタキで叩くが、繊維を全て潰すような叩き方ではない。口溶けと歯切れを良くするための叩きだ。長い牛刀の峰を立てて丁寧に肉の裏表の筋を切り、小麦粉をつける。
この小麦粉の余分についているのを念入りに、とても丁寧に落としてから、卵にくぐらせる。みていたら、その溶き卵からひきだしたのちも、よーく肉を振って、余分な卵液を落としている。結果、小麦粉と卵はごく最低限度の薄さでしか肉にまとわれていない。
それを、一片一片がとても大きく存在感のある生パン粉の海に投じる。そこからのパン粉づけがまたみもので、実に丁寧に、ゆっくりやわらかく手を押し当てて、パン粉をつけていく。もちろん卵液の二度づけなどしない。あれだけ最低限度の卵液に削いでいるから、パン粉のつきが悪いのでは無いかと心配になるが、フンワリ厚みのあるパン粉づけがなされた。
そして、この店の代名詞とも言える、油が湛えられた厚い銅鍋が二台。低温と高温、温度帯が違う鍋が並んでいる。パン粉を数回入れて油温をみる。なかなか入れない、ということは、温度の調整幅がとてもシビアなのだろう。やっとカツを投入。しばしいじらぬが、散ったパン粉を全て網でとりさるので、油は実に透明クリアを保っている。
そしてトンカツ好きにはたまらない、油鍋またぎの瞬間。油温の違う第2の鍋に投入して、衣をカリッとさせ肉の水分量を最適なまでに仕上げて、太いさいばしで引き上げる。
ここから店主が油を切るためにトンカツを振ること、すくなくとも30回。油を切って、切って、切りまくる。強く振るときに少しでも箸がずれると、トンカツがどこかへ飛んで行くし、そうでなくとも衣が剥がれるだろう。すごい圧力でトンカツを締め、油を徹底的に切る。小麦粉も卵液もそうだが、一切の余分を嫌うのだ。
油を徹底的に切って網に置き、余熱で最後の仕上げ。いつのまにかキャベツと銅網が盛られた皿が用意される。
ここで取り出したのが、あの、特徴的な形状の刃をもつトンカツ包丁だ。衣と肉の接地面を崩さないようにサキン!サキン!サキン!とかつを切っていく。
「おまたせいたしました」
と出てきたトンカツは、もはや後光が射していた。20年以上ぶりとなったこのトンカツの味がどうだったか、、、そんなの、書くまでもないでしょう。
その店の名は、「かつ好」。
ぼくは7月に控えた事務所の引越をやめようかと、半分本気で思い始めてしまったのだ。
※「かつ好」は「かつよし」と読む。念のため。